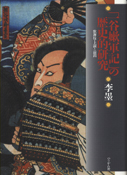「一谷嫩軍記」の歴史的研究 歌舞伎・上演と演出
「一谷嫩軍記」の歴史的研究 歌舞伎・上演と演出
(グローバルCOE研究員 博論成果出版)
著者:李 墨(2008年度グローバルCOE客員講師)
【博論成果出版について】
演劇博物館グローバルCOEでは、若手研究者の学位論文のうち、特に優れた内容のものを選考し、単行本として刊行している。
【内容】
宝暦2年から明治36年にいたるまでの「一谷嫩軍記」の発展と変遷を縦軸とし、各時代に生まれた劇術や他の作品と関係を横軸として、今日まで伝わる歌舞伎作品の表現力、受容、役者への投影等の変遷を追う。
2009年3月31日発行
A5判・488ページ
ぺりかん社
定価:9500円+税
【目次】
刊行によせて=竹本幹夫
序=古井戸秀夫
序 章 歌舞伎演出の視座
一 理念としての歌舞伎演出
二 作品の先行研究
三 本書の研究方法・研究範疇・構成
第一章 歌舞伎「一谷嫩軍記」初期の演出
第一節 歌舞伎「一谷嫩軍記」初演
一 江戸の初演
二 大坂の初演―中村十蔵座
三 京都での移入
第二節 熊谷の役柄と上演形態
一 熊谷の役割
二 第一期の上演形態
三 第一期上演の流れ
第三節 雛助・仁左衛門の台本分析
一 初演雛助本の書誌分析・その性格
二 七代目仁左衛門本の書誌分析・その性格
三 「陣門組討」の台本構成
四 「熊谷陣屋」の台本構成
五 雛助と仁左衛門の熊谷像
第二章 化政期以降の台本研究
第一節 台本の書誌分析・その性格
一 三代目歌右衛門本の書誌とその性格
二 多見蔵時代書込み本の性格
三 八代目市川団十郎本の性格
四 四代目市川小団次本の性格
五 四代目中村芝翫本の性格
六 竹柴金三本の性格
七 竹柴清吉本の性格
第二節 「陣門組討」の台本構成と演出
一 場面の構成
二 原作との交合
三 演出分析
第三節 「熊谷陣屋」の台本構成
一 場面の構成
二 原作との交合
第三章 演出の大成
第一節 演出の大成
一 歌舞伎独自の上演形態の確立
二 台本構成の独自性
三 歌舞伎独自の演出の確立
第二節 三代目三津五郎の領分
一 丸坊主の演出
二 三代目三津五郎の領分
第三節 三代目歌右衛門の「梅玉の型」
一 四つの転機点に見られる演出の消長
二 「梅玉の型」の演出―(一)陣門・組討
三 「梅玉の型」の演出―(二)熊谷陣屋
第四章 古典化への歩み
第一節 七代目団十郎の「成田屋の型」
一 七代目団十郎の熊谷
二「成田屋の型」の演出―(一)熊谷陣屋
三「成田屋の型」の演出―(二)陣門組討
第二節 四代目歌右衛門・三代目芝翫の演出の古典化
一 四代目歌右衛門の継承
二 三代目中村芝翫の継承と古典化
第三節 新しい作品の発生と展開
一 三津五郎の四段目復活と忠度組討の増補
二 歌右衛門の「須磨都源平躑躅」
三 団十郎の「蓮生譚」
第四節 多様化する上演形態
一 上演形態
二 古典化における他の側面
三 浜芝居の流れ
第五章 演技と表現の変遷
第一節 腹を割る系譜
一 江戸期における腹を割る系譜
二 「親子の情愛」の成立
第二節 演技に纏わる写実の変遷
一 「物好き」から見る写実の流れ
二 故実と本式
三 明治の写実
参考資料
掲載図版一覧
あとがき
人名索引